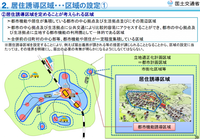公営住宅の本来の在り方(長野市答弁編)
2019年04月19日
生活困窮者の公営住宅支援につきまして行政側の答弁を載せていきます。
質問は前回の記事にありますので、ご確認下さい。
<建設部長 答弁>
住宅対策における、特に低所得者や高齢者などの住まいの貧困について、長野市の現状はどのようになっているかについてお答えいたします。
まず、昨年2月に策定いたしました長野市第三次住宅マスタープランでは、国の住宅・土地統計調査の結果等を基に、本市における住まいの現状を調査しております。
 この調査結果によると、本市では1世帯当たりの人数が減少し、世帯の小規模化が進んでいる他、年収300万円未満の世帯割合が増加傾向にあります。また、高齢者世帯が増加し続け、特に単身の高齢者世帯が急増している状況となっております。
この調査結果によると、本市では1世帯当たりの人数が減少し、世帯の小規模化が進んでいる他、年収300万円未満の世帯割合が増加傾向にあります。また、高齢者世帯が増加し続け、特に単身の高齢者世帯が急増している状況となっております。
次に、市内の住宅ストックの状況についてでありますが、住宅総数は増加を続け、平成25年の1世帯当たりの住宅数は1.17戸であり、量的には充足しております。持ち家率も増加傾向にある中、65歳以上の持ち家率は夫婦世帯が9割を超えるのに対し、単身世帯は7割程度にとどまり、3割の高齢単身者は民間借家や公営住宅に居住しております。
最近の市営住宅の応募状況につきましても、単身世帯や高齢者世帯の応募が多いことから、平成30年10月から3DKの市営住宅の一部に単身者も入居できるよう入居要件を見直し、高齢単身者や若年単身者が応募できる住宅を増やしております。
したがいまして、議員の御質問にございます20歳を迎え、児童自立援助ホームを退所しなければならず、市営住宅に住みたいといったケースにつきましても、これまでに比べて申し込みしやすい状況となっております。
本市では、低所得者や高齢者など、一般のアパートなどへ入居が困難な方のお住まいには市営住宅を基本と考えており、今後も居住性の向上や長寿命化の改善工事を進めるとともに、入居基準や募集方法の見直しなどにより、適正な市営住宅の供給を図ってまいります。
<保健福祉部長 答弁>
住まいの支援に関して、福祉の立場でお答えいたします。
議員の御指摘の若者の事案も含めて、低所得や生活困窮など、住まいの貧困の現状の把握につきましては、まいさぽ長野市の自立相談支援事業の相談窓口において個別案件の相談を受け付けし、生活状況や悩みの把握を行っております。
家賃を払えず、住居を失うおそれがある、老朽化し転居を求められている、保証人が見付からない、緊急連絡先になる人がおらず、契約できないなどの相談が寄せられております。
 相談件数は、平成29年度227件であり、相談全体の14パーセントが住居相談でございます。このうち、失業のため家賃を支払うことが困難になった方には、住居確保給付金の支給をしており、また、緊急に食事、住居の確保が必要な方には一時生活支援事業による宿泊施設の提供を行っております。また、低家賃の住居への転居では公営住宅の募集状況を提供しております。
相談件数は、平成29年度227件であり、相談全体の14パーセントが住居相談でございます。このうち、失業のため家賃を支払うことが困難になった方には、住居確保給付金の支給をしており、また、緊急に食事、住居の確保が必要な方には一時生活支援事業による宿泊施設の提供を行っております。また、低家賃の住居への転居では公営住宅の募集状況を提供しております。
なお、賃貸住宅につきましては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、この法律の一部改正に伴いまして、保証人が見付からない方には、長野県社会福祉協議会による長野県あんしん創造ねっとの入居保証、生活支援事業を御案内しております。
このような住まいの支援を必要としている方に対し、必要な情報を的確に届けるよう、より一層まいさぽ長野市の周知、PRに努めてまいりたいと考えております。
質問は前回の記事にありますので、ご確認下さい。
<建設部長 答弁>
住宅対策における、特に低所得者や高齢者などの住まいの貧困について、長野市の現状はどのようになっているかについてお答えいたします。
まず、昨年2月に策定いたしました長野市第三次住宅マスタープランでは、国の住宅・土地統計調査の結果等を基に、本市における住まいの現状を調査しております。
 この調査結果によると、本市では1世帯当たりの人数が減少し、世帯の小規模化が進んでいる他、年収300万円未満の世帯割合が増加傾向にあります。また、高齢者世帯が増加し続け、特に単身の高齢者世帯が急増している状況となっております。
この調査結果によると、本市では1世帯当たりの人数が減少し、世帯の小規模化が進んでいる他、年収300万円未満の世帯割合が増加傾向にあります。また、高齢者世帯が増加し続け、特に単身の高齢者世帯が急増している状況となっております。次に、市内の住宅ストックの状況についてでありますが、住宅総数は増加を続け、平成25年の1世帯当たりの住宅数は1.17戸であり、量的には充足しております。持ち家率も増加傾向にある中、65歳以上の持ち家率は夫婦世帯が9割を超えるのに対し、単身世帯は7割程度にとどまり、3割の高齢単身者は民間借家や公営住宅に居住しております。
最近の市営住宅の応募状況につきましても、単身世帯や高齢者世帯の応募が多いことから、平成30年10月から3DKの市営住宅の一部に単身者も入居できるよう入居要件を見直し、高齢単身者や若年単身者が応募できる住宅を増やしております。
したがいまして、議員の御質問にございます20歳を迎え、児童自立援助ホームを退所しなければならず、市営住宅に住みたいといったケースにつきましても、これまでに比べて申し込みしやすい状況となっております。
本市では、低所得者や高齢者など、一般のアパートなどへ入居が困難な方のお住まいには市営住宅を基本と考えており、今後も居住性の向上や長寿命化の改善工事を進めるとともに、入居基準や募集方法の見直しなどにより、適正な市営住宅の供給を図ってまいります。
<保健福祉部長 答弁>
住まいの支援に関して、福祉の立場でお答えいたします。
議員の御指摘の若者の事案も含めて、低所得や生活困窮など、住まいの貧困の現状の把握につきましては、まいさぽ長野市の自立相談支援事業の相談窓口において個別案件の相談を受け付けし、生活状況や悩みの把握を行っております。
家賃を払えず、住居を失うおそれがある、老朽化し転居を求められている、保証人が見付からない、緊急連絡先になる人がおらず、契約できないなどの相談が寄せられております。
 相談件数は、平成29年度227件であり、相談全体の14パーセントが住居相談でございます。このうち、失業のため家賃を支払うことが困難になった方には、住居確保給付金の支給をしており、また、緊急に食事、住居の確保が必要な方には一時生活支援事業による宿泊施設の提供を行っております。また、低家賃の住居への転居では公営住宅の募集状況を提供しております。
相談件数は、平成29年度227件であり、相談全体の14パーセントが住居相談でございます。このうち、失業のため家賃を支払うことが困難になった方には、住居確保給付金の支給をしており、また、緊急に食事、住居の確保が必要な方には一時生活支援事業による宿泊施設の提供を行っております。また、低家賃の住居への転居では公営住宅の募集状況を提供しております。なお、賃貸住宅につきましては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、この法律の一部改正に伴いまして、保証人が見付からない方には、長野県社会福祉協議会による長野県あんしん創造ねっとの入居保証、生活支援事業を御案内しております。
このような住まいの支援を必要としている方に対し、必要な情報を的確に届けるよう、より一層まいさぽ長野市の周知、PRに努めてまいりたいと考えております。
コメントいただき有難うございます。お返事お待ちください。