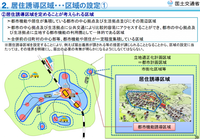長野市にある「中間教室」って・・・【答弁篇】
2020年07月01日
長野市議会6月定例会においてワタシが行った質問について、行政側から答弁をもらいましたので、皆さんに見ていただきたいと思います。
今回は「中間教室について」の答弁になります。
(質問は前回載せてますのでチェックしてみてください)
以下、答弁・・・。
【教育次長】
中間教室について。
まず、中間教室に通室している児童・生徒の小・中学校別の割合についてだが、昨年度は小学生が約25パーセント、中学生は約75パーセントで、今年度は4月末現在、小学生は約33パーセント、中学生は約67パーセントとなっている。
 次に、学力の遅れを出さないための対策について。
次に、学力の遅れを出さないための対策について。
本市では、中間教室において児童・生徒の社会的自立を第1の目的とし、自立心の育成を目指した活動を行えるよう、個々の児童・生徒の実態に応じた支援をしている。
その中で、学習の遅れが生じないように、各中間教室の日課の中に学習の時間を設けております。学習の時間では、教員免許を有する指導員が通室生の在籍校と連絡をとり合いながら、それぞれの子の学習進度に合わせた教材やプリント等を配付し、可能な限り個別指導を行い、できた、分かったという実感と成就感が持てるよう支援をしているところである。
3点目の中間教室での出席状況の把握について。
中間教室では、月ごとに日々の出席の状況や通室したときの様子を在籍校に報告し、在籍校からはコメントを記入して返却する等、双方で状況が共有できるようになっている。
なお、昨年10月に文部科学省から出された不登校児童・生徒への支援の在り方についてにも示されているとおり、中間教室への通室は出席として認められている。
また、フリースクールなどの民間施設においても出席扱い等の条件がそろえば、学校長の判断で出席として認められるようになっている。
 4点目の中間教室を利用するまでの対応について。
4点目の中間教室を利用するまでの対応について。
本市では、小・中学校において児童・生徒に登校渋りの兆候が見られたとき、学校内で情報共有し、児童・生徒の気持ちをくみ取りながら家庭と相談し、可能な範囲で登校や放課後登校、校内の中間教室の利用等を提案している。
その際、市の中間教室の紹介については、議員指摘のとおり、児童・生徒によっては遠方から通うことになる場合もあるので、まずは在籍する学校で可能な限りの対応を行い、校内で行える支援を経てもなお不登校の状態が続いた場合には、児童・生徒の様子や保護者の考え、家庭の環境など様々な面を踏まえ、市の中間教室を紹介することとしている。
それにより市の中間教室の利用に興味を持たれた場合には、中間教室へスムーズに適応できるよう、親子で見学をしたり、試しに通室を行ったりして利用に向けての抵抗感を少なくできるように努めている。
なお、市の中間教室は、国立、私立の学校を問わず、長野市に在住する児童・生徒であれば誰でも利用することが可能。
最後に、高校受験について。中学校においては、評点を出す際、教科ごとに複数の観点が定められており、これらを総合的に判断して評定がなされるので、出席日数不足や定期試験未受験のみをもって評定がつかないということはない。
また、県立高校の入学者選抜においても、中学校からの調査書や学力検査の成績以外にも、各高校が受験生に行う面接や小論文等を総合的に判断し、合否の決定がなされている。
したがって、進学を望む全ての生徒において、登校していないことをもって様々な高校の選択ができないということはないと認識している。
今回は「中間教室について」の答弁になります。
(質問は前回載せてますのでチェックしてみてください)
以下、答弁・・・。
【教育次長】
中間教室について。
まず、中間教室に通室している児童・生徒の小・中学校別の割合についてだが、昨年度は小学生が約25パーセント、中学生は約75パーセントで、今年度は4月末現在、小学生は約33パーセント、中学生は約67パーセントとなっている。
 次に、学力の遅れを出さないための対策について。
次に、学力の遅れを出さないための対策について。 本市では、中間教室において児童・生徒の社会的自立を第1の目的とし、自立心の育成を目指した活動を行えるよう、個々の児童・生徒の実態に応じた支援をしている。
その中で、学習の遅れが生じないように、各中間教室の日課の中に学習の時間を設けております。学習の時間では、教員免許を有する指導員が通室生の在籍校と連絡をとり合いながら、それぞれの子の学習進度に合わせた教材やプリント等を配付し、可能な限り個別指導を行い、できた、分かったという実感と成就感が持てるよう支援をしているところである。
3点目の中間教室での出席状況の把握について。
中間教室では、月ごとに日々の出席の状況や通室したときの様子を在籍校に報告し、在籍校からはコメントを記入して返却する等、双方で状況が共有できるようになっている。
なお、昨年10月に文部科学省から出された不登校児童・生徒への支援の在り方についてにも示されているとおり、中間教室への通室は出席として認められている。
また、フリースクールなどの民間施設においても出席扱い等の条件がそろえば、学校長の判断で出席として認められるようになっている。
 4点目の中間教室を利用するまでの対応について。
4点目の中間教室を利用するまでの対応について。 本市では、小・中学校において児童・生徒に登校渋りの兆候が見られたとき、学校内で情報共有し、児童・生徒の気持ちをくみ取りながら家庭と相談し、可能な範囲で登校や放課後登校、校内の中間教室の利用等を提案している。
その際、市の中間教室の紹介については、議員指摘のとおり、児童・生徒によっては遠方から通うことになる場合もあるので、まずは在籍する学校で可能な限りの対応を行い、校内で行える支援を経てもなお不登校の状態が続いた場合には、児童・生徒の様子や保護者の考え、家庭の環境など様々な面を踏まえ、市の中間教室を紹介することとしている。
それにより市の中間教室の利用に興味を持たれた場合には、中間教室へスムーズに適応できるよう、親子で見学をしたり、試しに通室を行ったりして利用に向けての抵抗感を少なくできるように努めている。
なお、市の中間教室は、国立、私立の学校を問わず、長野市に在住する児童・生徒であれば誰でも利用することが可能。
最後に、高校受験について。中学校においては、評点を出す際、教科ごとに複数の観点が定められており、これらを総合的に判断して評定がなされるので、出席日数不足や定期試験未受験のみをもって評定がつかないということはない。
また、県立高校の入学者選抜においても、中学校からの調査書や学力検査の成績以外にも、各高校が受験生に行う面接や小論文等を総合的に判断し、合否の決定がなされている。
したがって、進学を望む全ての生徒において、登校していないことをもって様々な高校の選択ができないということはないと認識している。
コメントいただき有難うございます。お返事お待ちください。